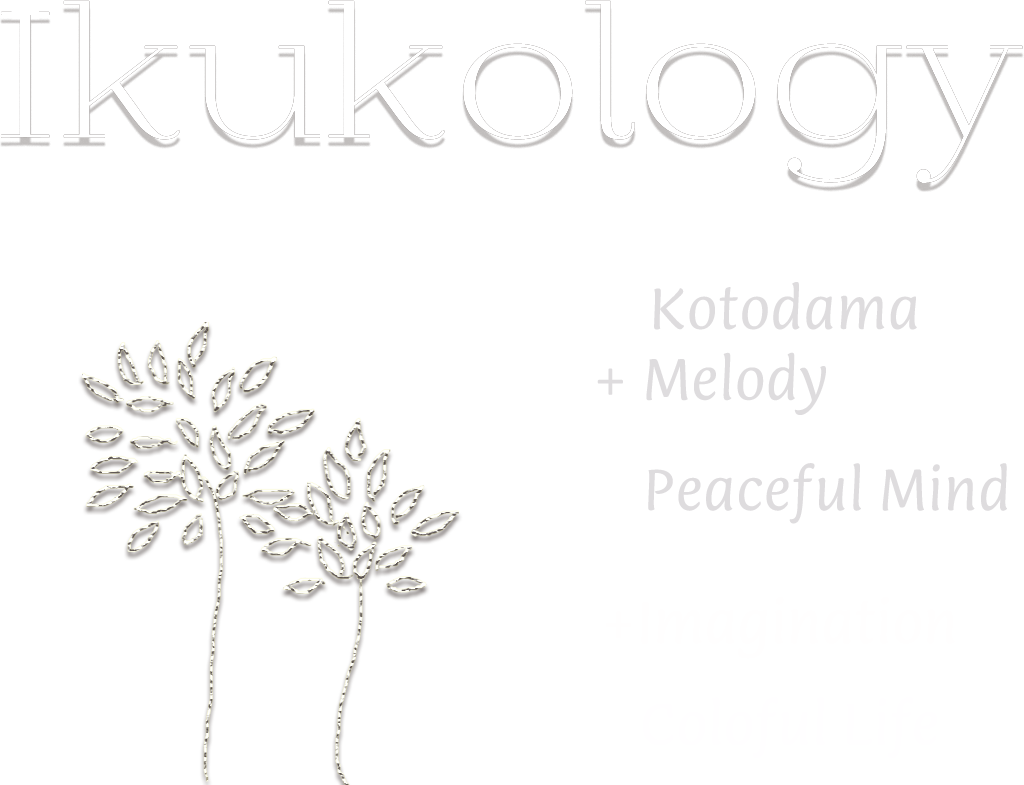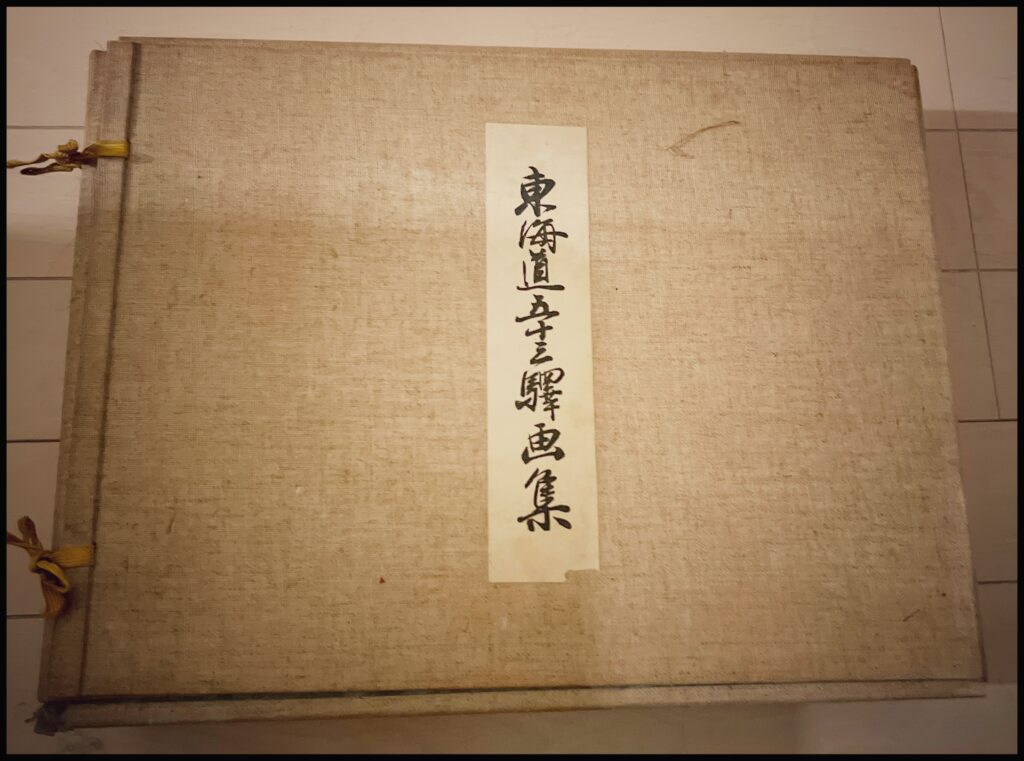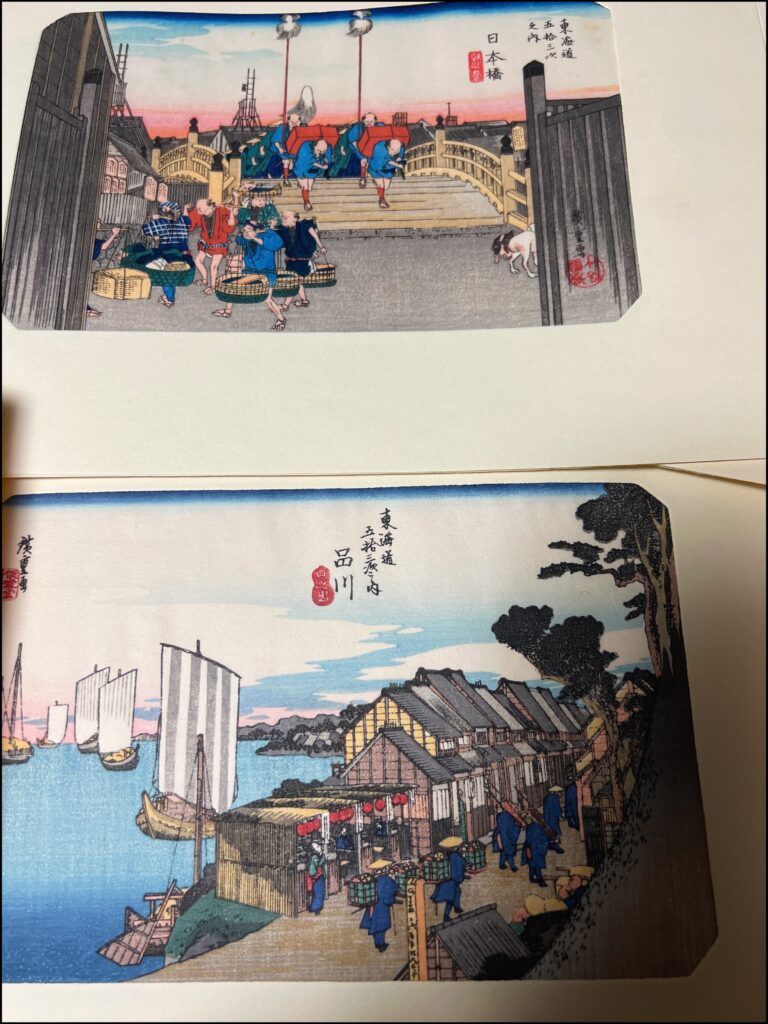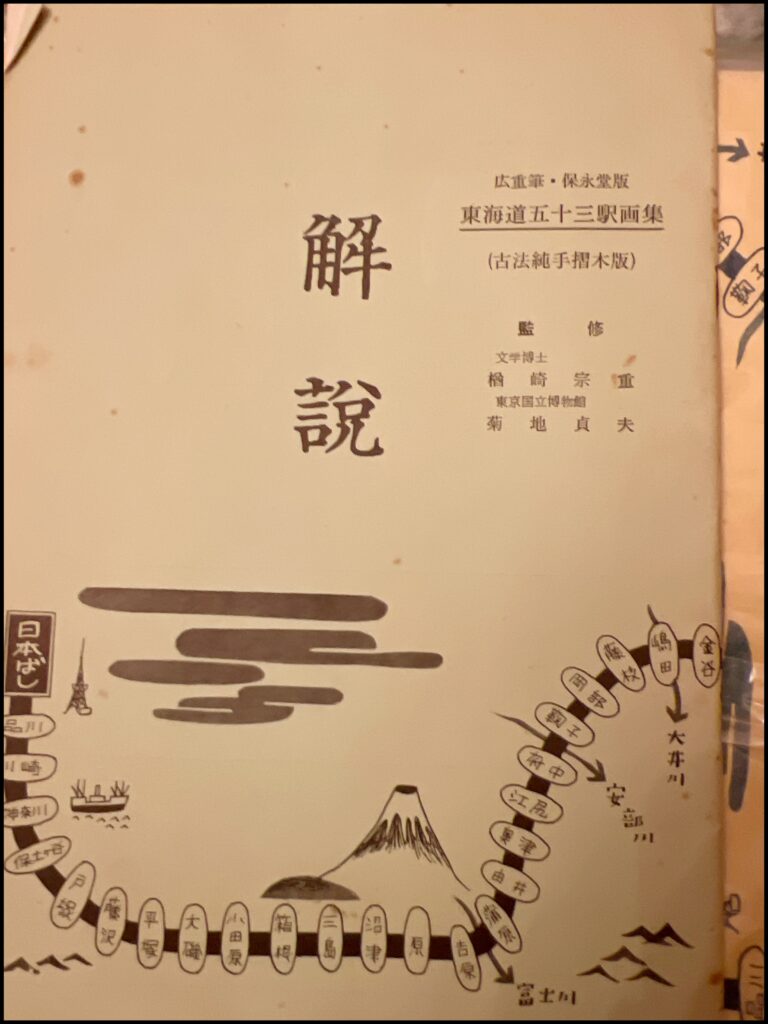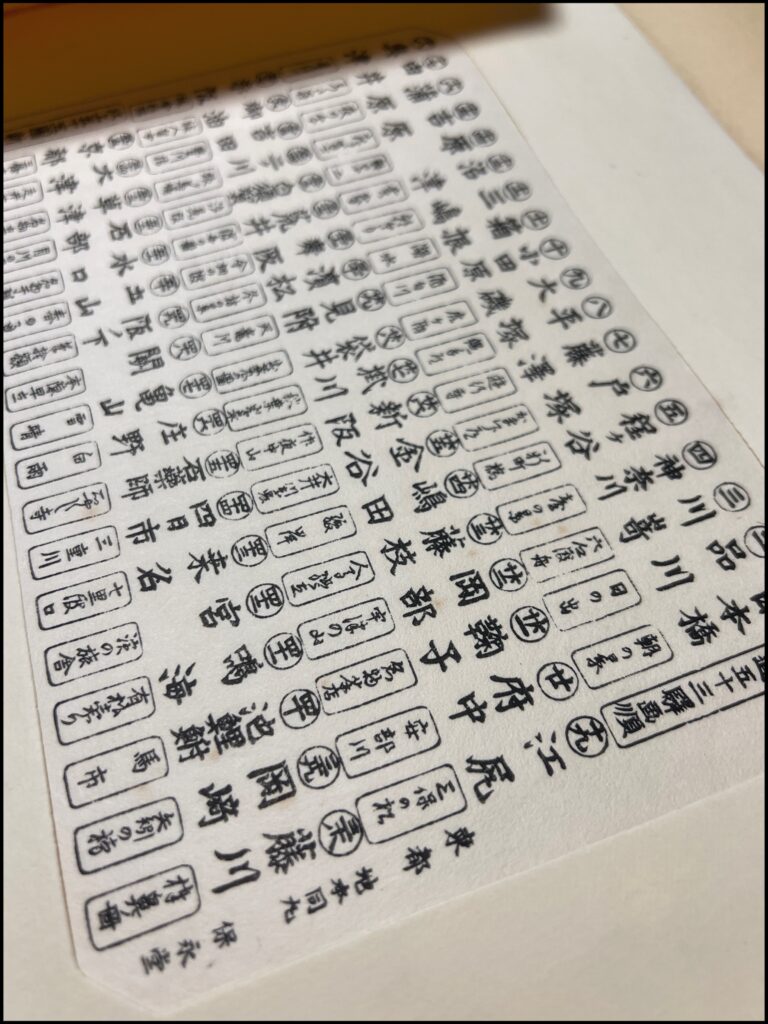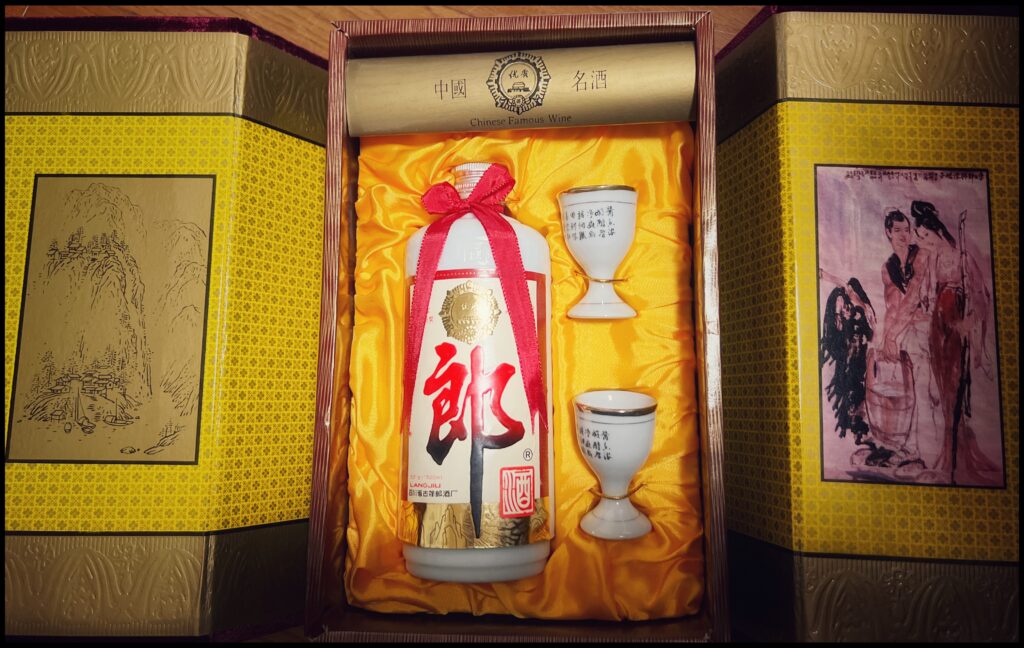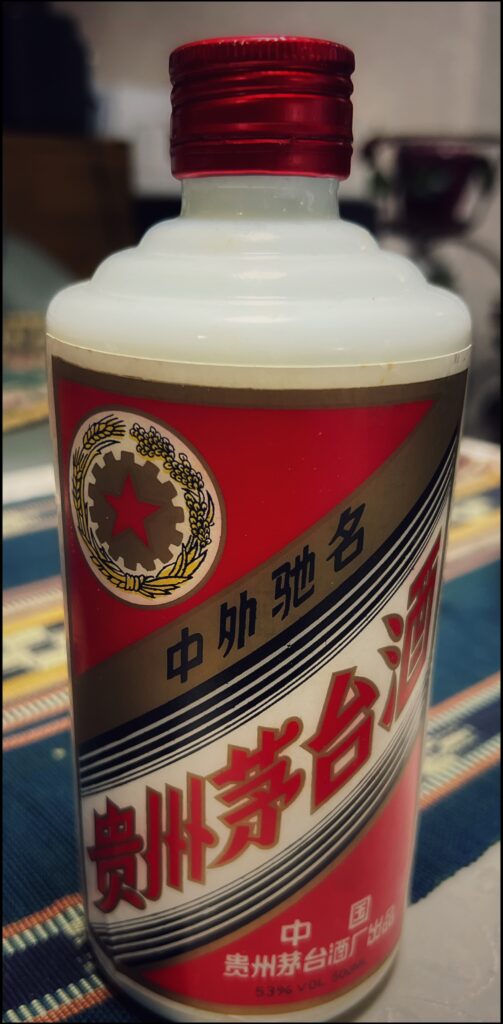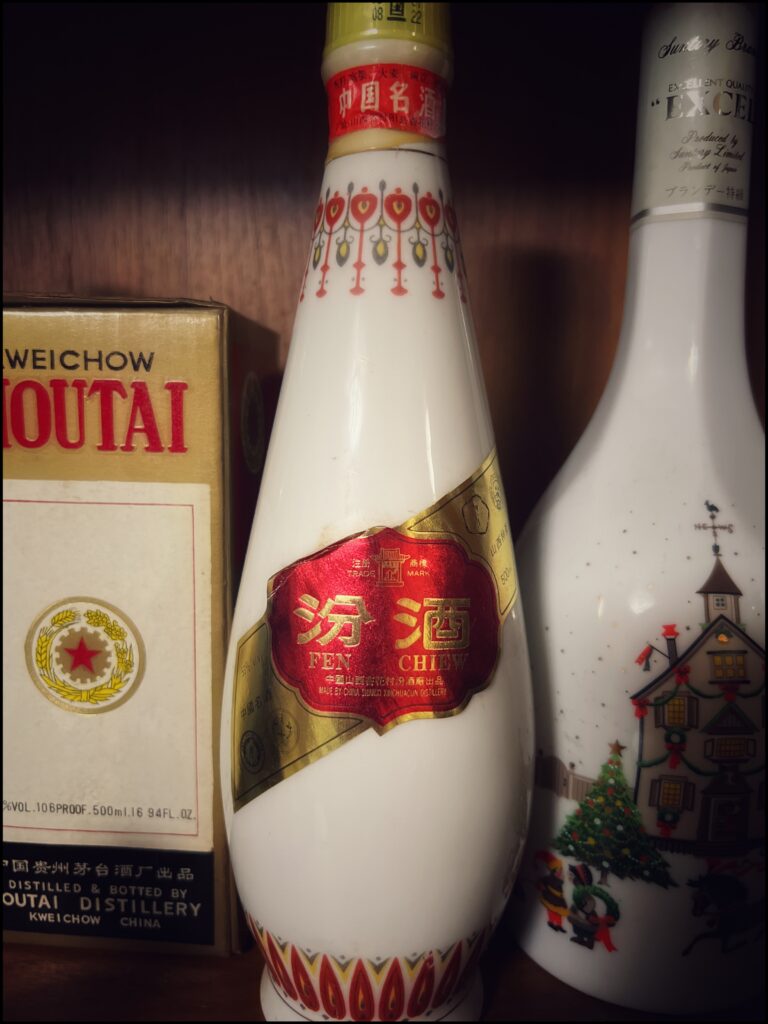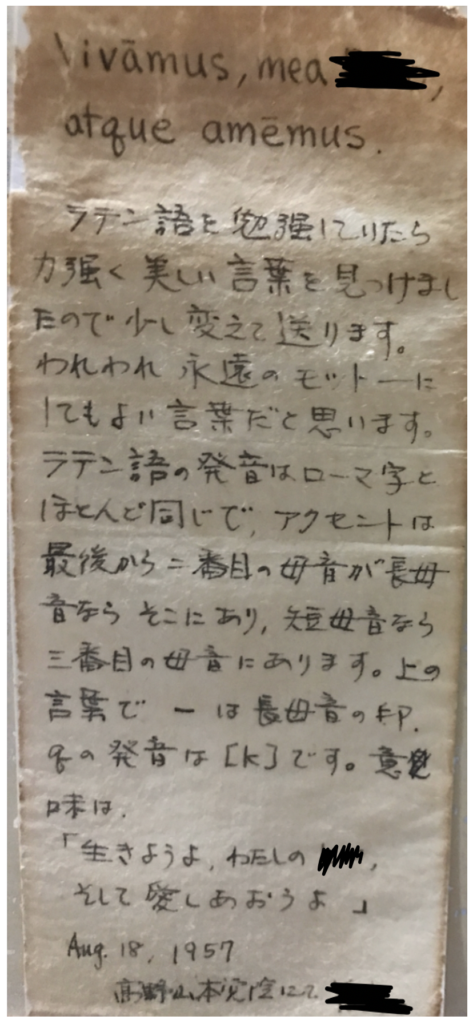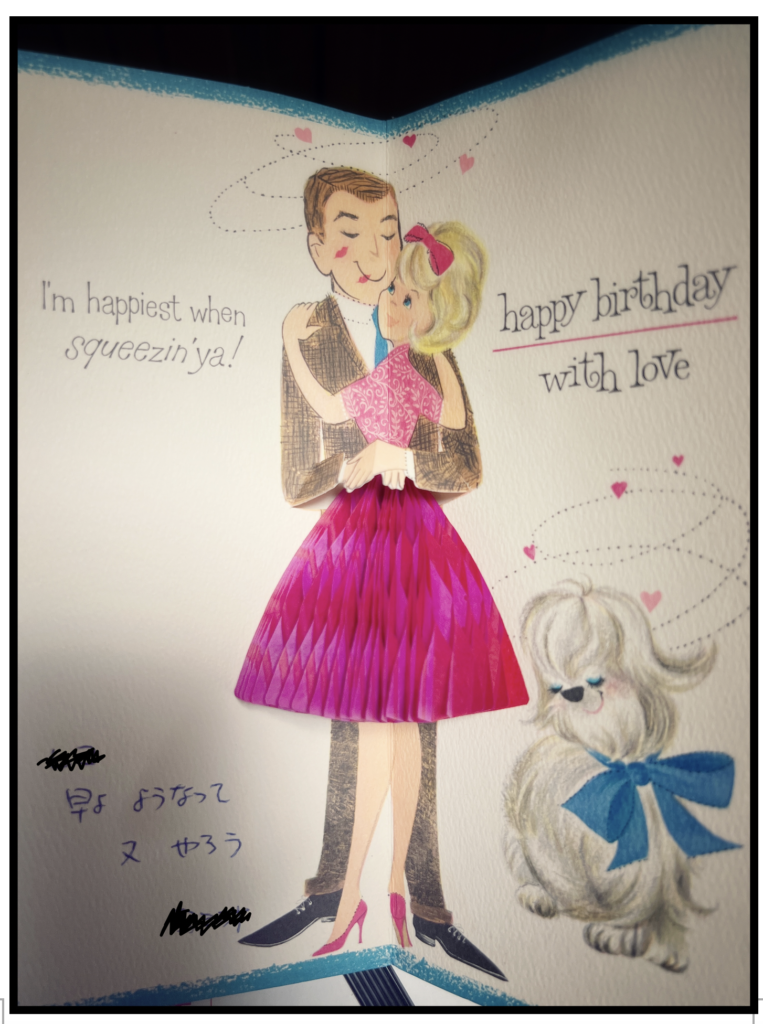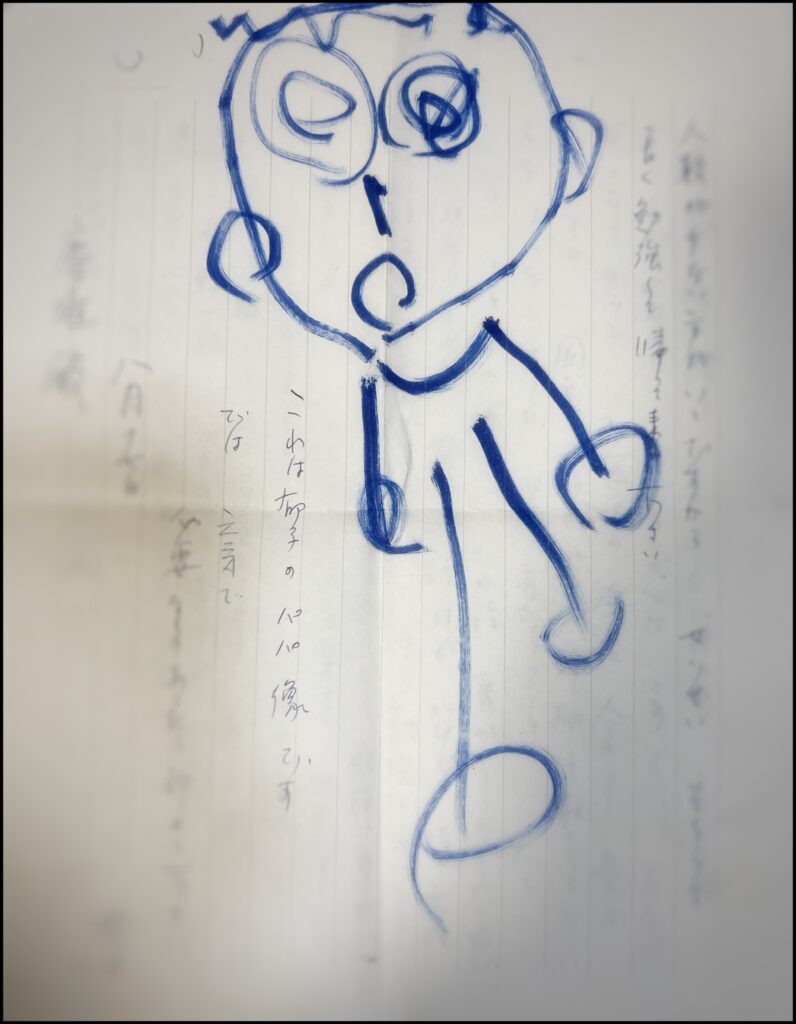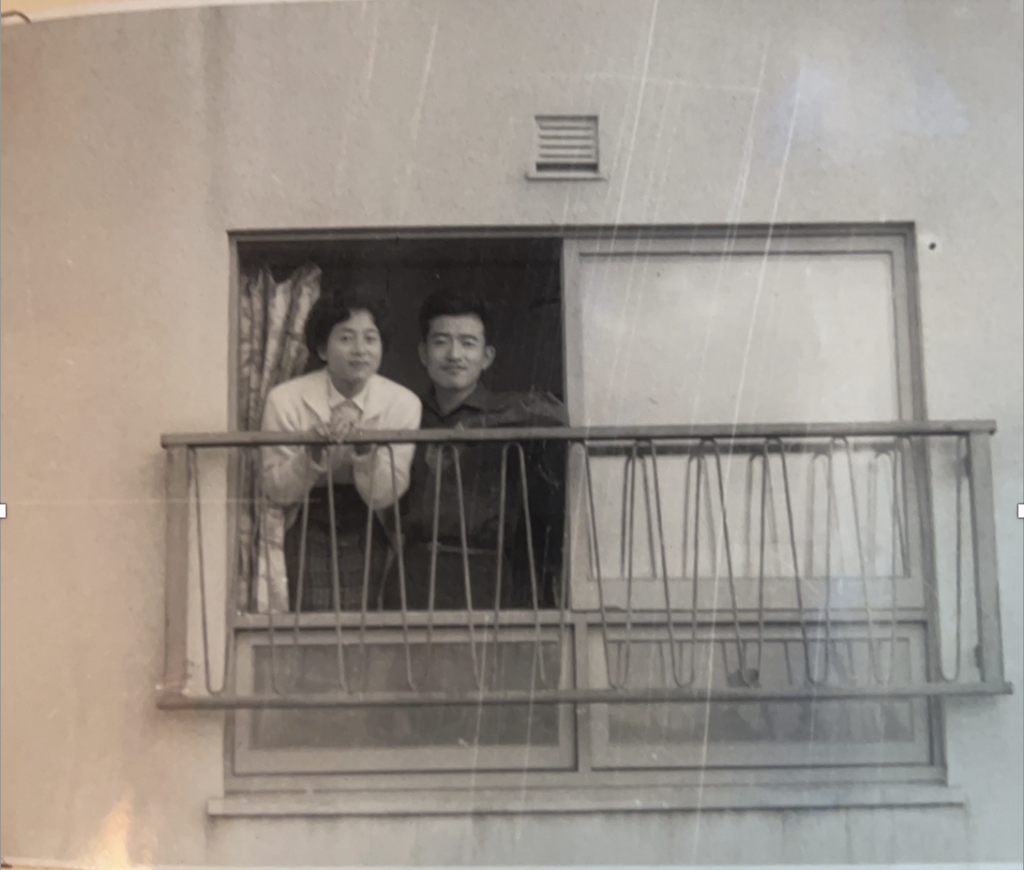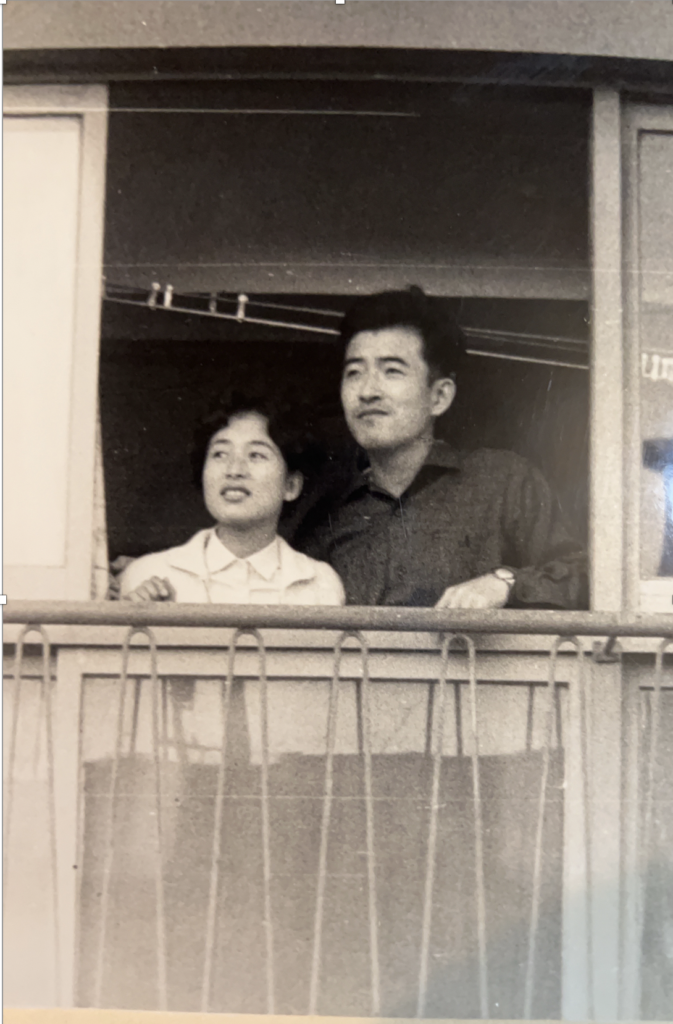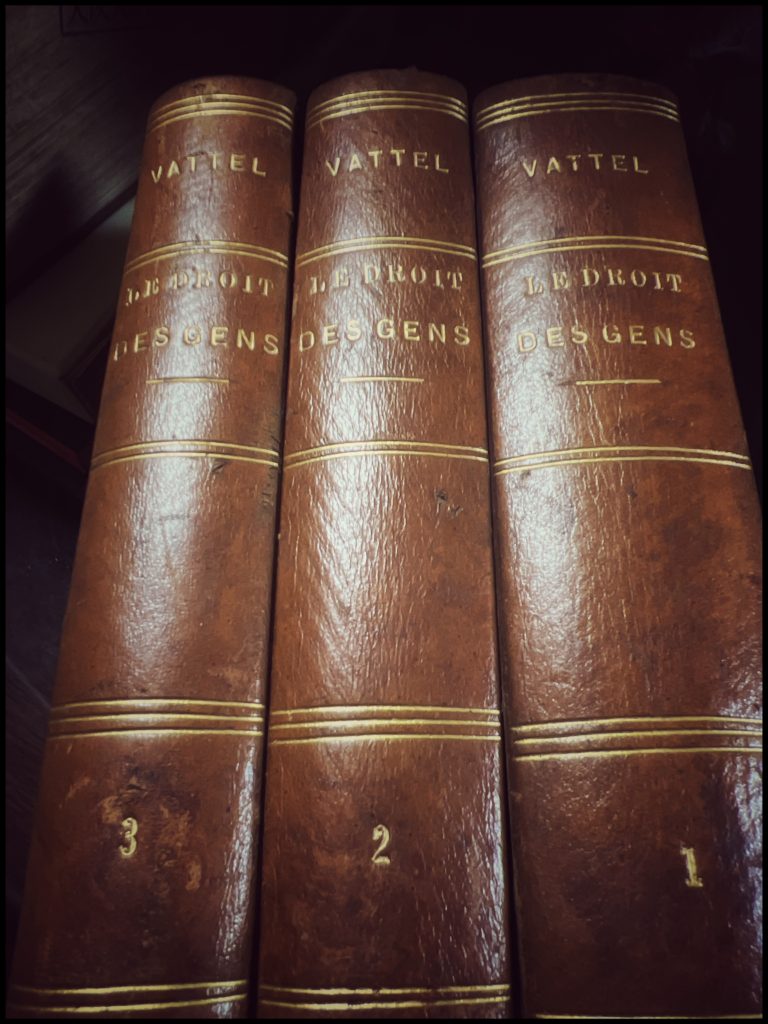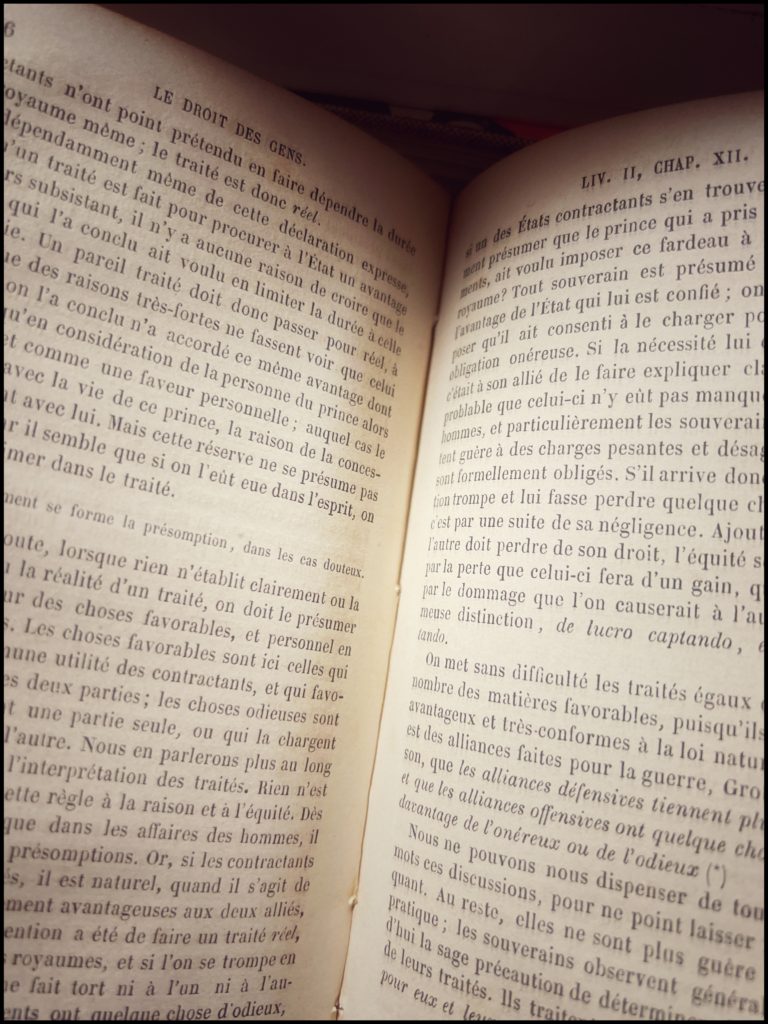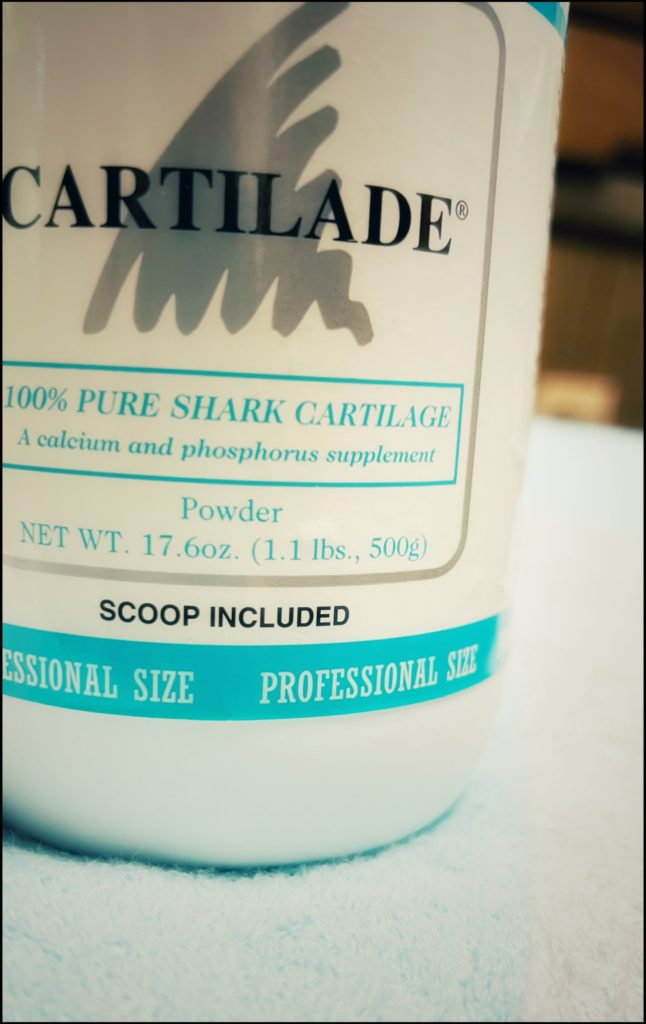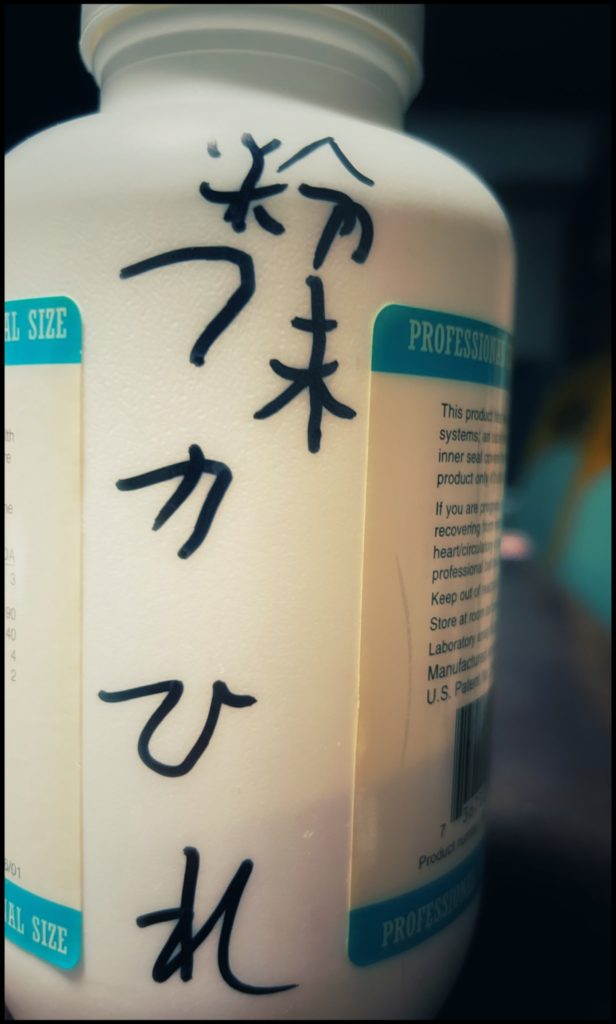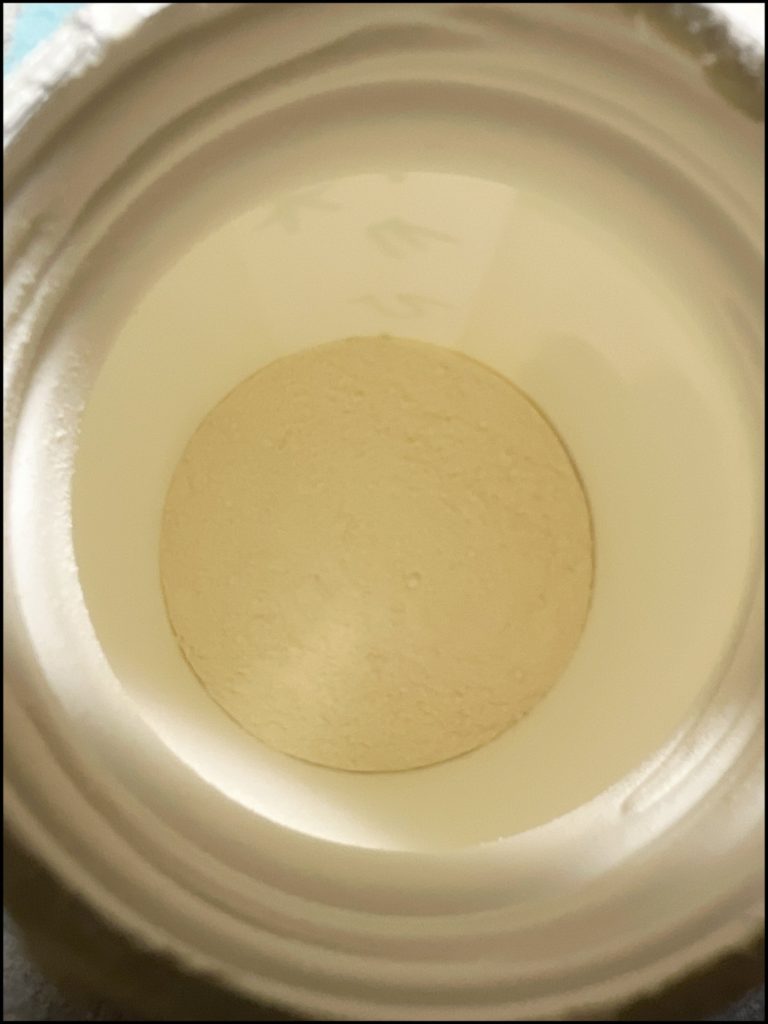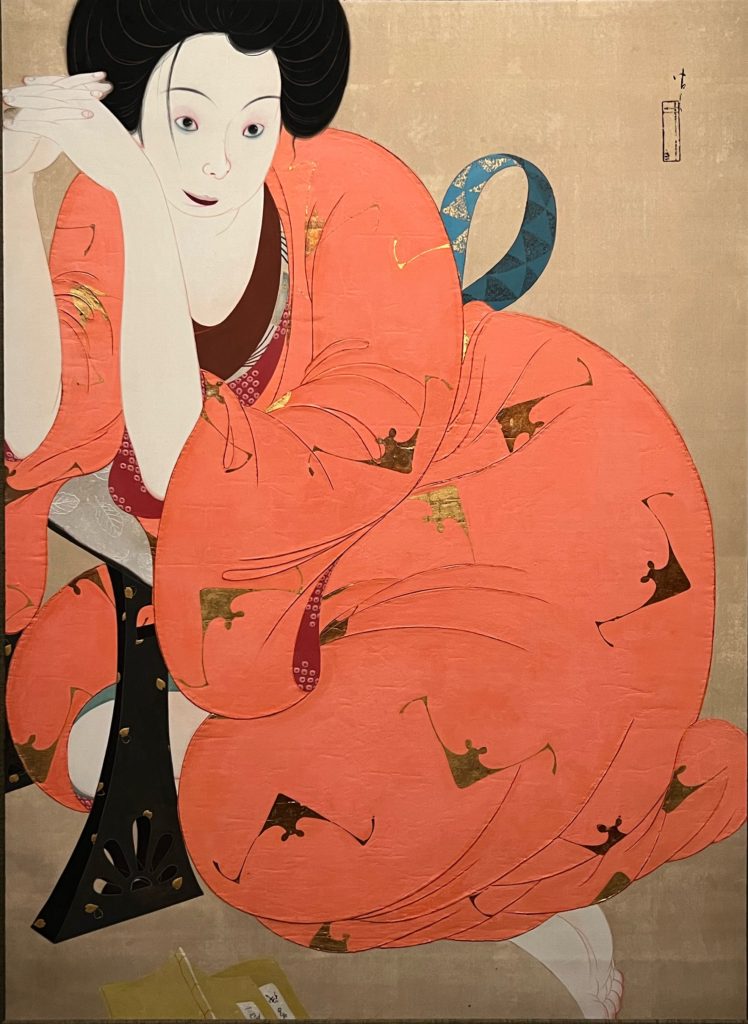「お宝か?」編
遂にきたか。
2階の物入れの奥の奥から、
見るからに物々しいイデタチの、
バリバリお宝風がでてきたヨ。
は〜い、教科書にでてきたヤツ!
歴史に疎い私でも知っているメジャー級。
東海道と い・え・ばっ
膝栗毛・・・やのうて、五十三次か。
「ひざくりげ〜」の方がインパクト大やったな。
サウンド的に。
しかし、何がどう違うのやったっけ。
改めてお勉強。
「東海道中膝栗毛」は江戸時代後期の戯作者、十返舎一九の代表作で、享和2年(1802)から文化6年(1809)にかけて出版された滑稽本。日常生活を風刺したお話やね。
「東海道五十三次」は江戸時代に整備された五街道の一つ、東海道に置かれた53の宿場のことで、しばしば浮世絵や和歌に取り上げられた。とある。
いずれも、日本初・旅ブームの火付け役。
そして今、私の手にある物は・・・
ずっしり重い。
これは浮世絵、ホンマモンかもしれない!
期待を込めて、
文字通り、
紐解く。
おーーーーーっ。
うつくしい。
うつくしすぎる。
ちょっと鮮やかすぎやしないか。
年代物にしては・・・。
もしや本物ではない?
木版画であるからして、コピーもの?
・・・どう捉えていいのかわからない。
と、その時、心の声がつぶやいた。
(以下 心の声)
「あたりまえだろうがっ!
平民の拙宅の物入れに
原画があるわけなかろうがっ!」
(あまりに美しい色彩に目が醒める)
しかし、本物の分身であることに間違いはない。
” 広重筆 “とあるではないか。
絵師、歌川広重だ。
「広重は東海道五十三次によって風景版画の第一人者となり、東海道は広重によって有名になった。東海道の風物、地誌を描いた絵は、江戸時代の初期から、下つて葛飾北斎に至るまで、いろいろの姿で描かれているが、広重のように芸術的な香りをもつものは少ない」
と解説にある。
全ての絵の外装をとって眺めたわけではないが、
確かにその芸術性は庶民の目で見ても楽しめる要素満載である。
残念ながら発行年月日が見当たらない。
しかし、500部の限定出版と書かれているので
貴重ではあると思う。
巨匠の絵を蘇らせてくれた技術者の方々に
じわじわと感謝の念が湧いてきた。
歴史の断片がここにある。
当面我が家に保管することになるので、
近々うちに家飲みに来る人、
酒をちびちびやりながら、古の五十三次を共に
バーチャルトリップしようではないか。
ちなみに今日はマイ・バースデー。
嬉しいサプライズプレゼントとなった。