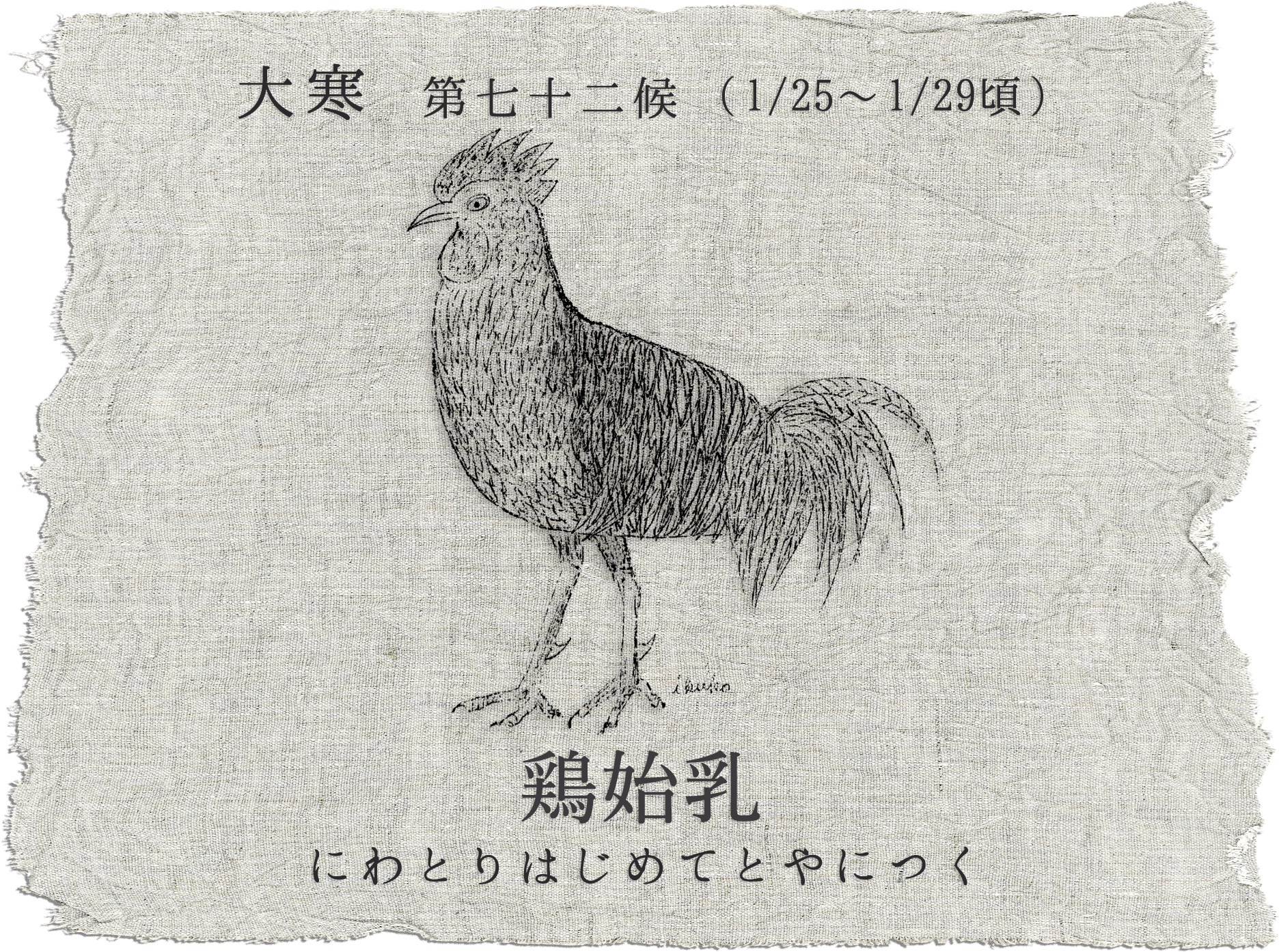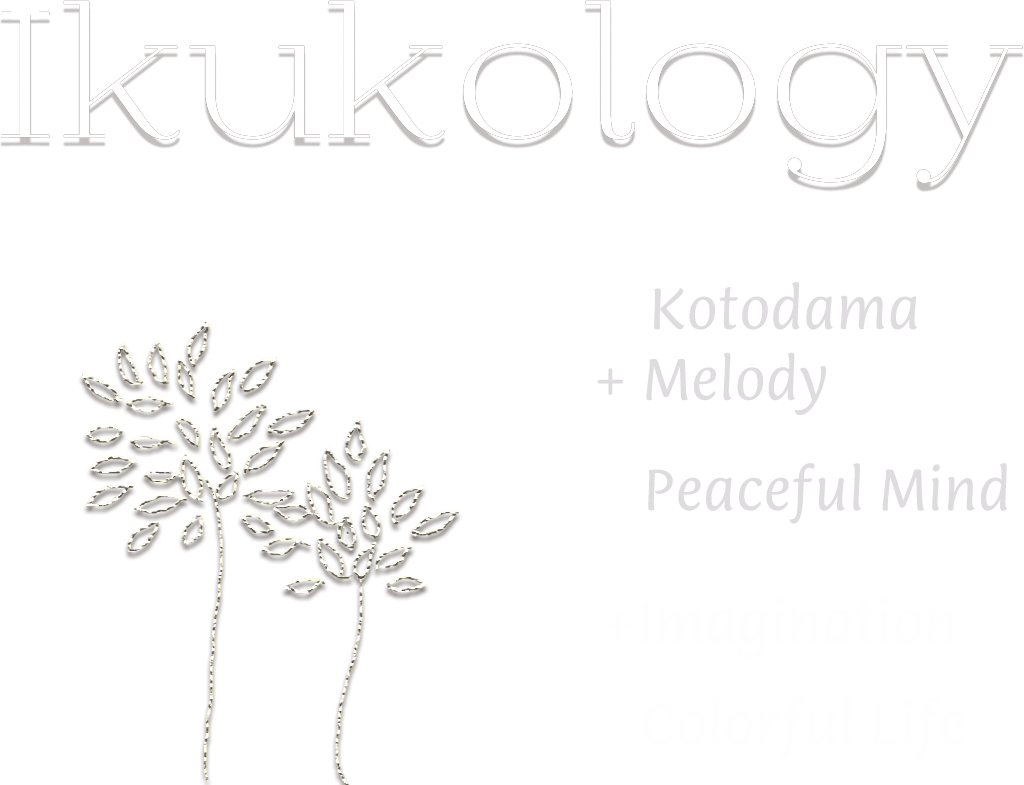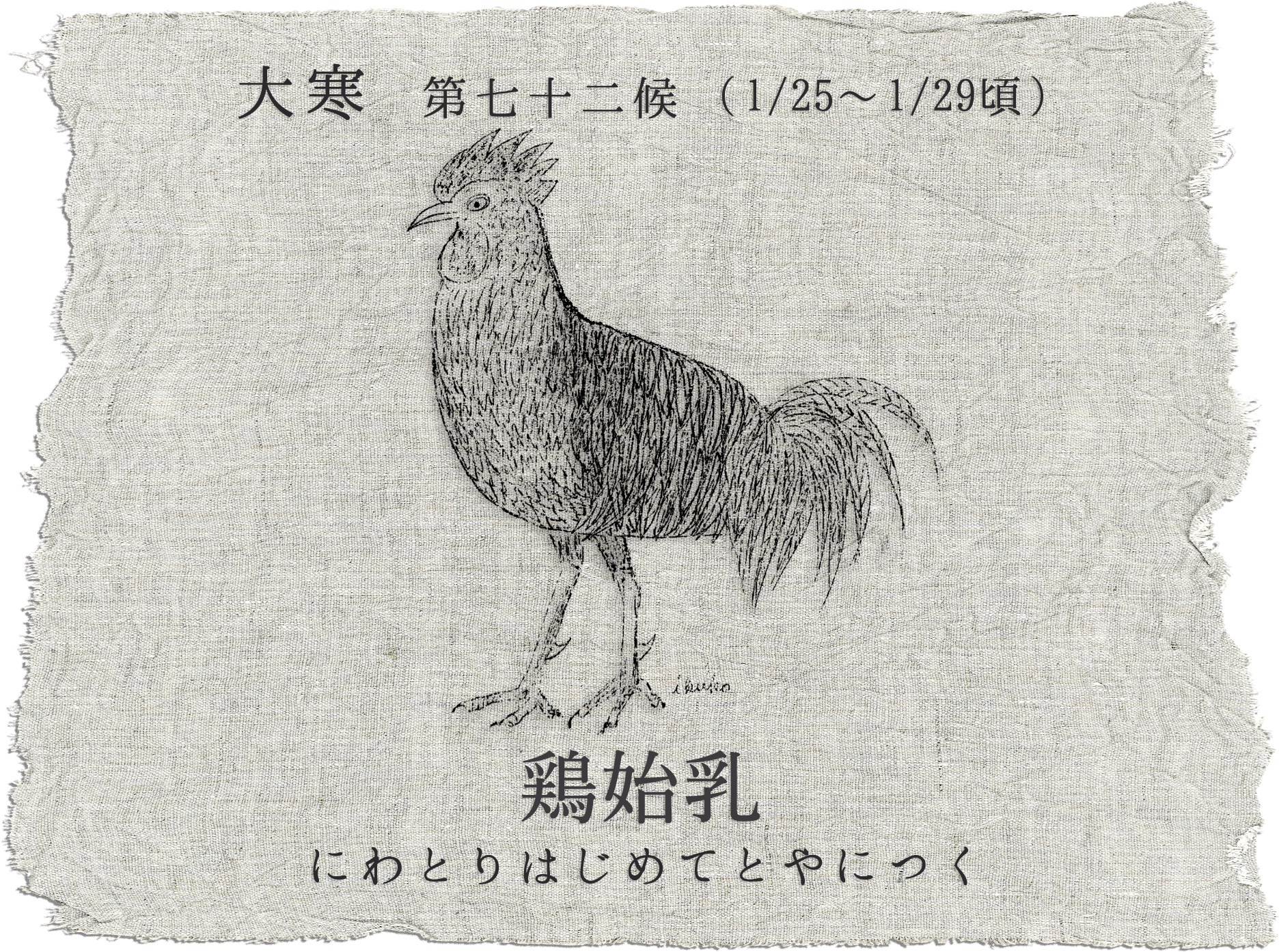春の気配を感じた鶏が卵を産み始める頃
「とや」とは何ぞや?「とや」=鳥屋。鳥を飼っている小屋の事。「鳥屋(とや)に就(つ)く」は、鶏が産卵のために巣に籠るという意味だそうです。現在の鶏は一年中卵を産むように飼育されていますが、自然の状態の鶏は冬はほとんど卵を産まず、産卵期は春から初夏にかけて。日照時間が長くなるにつれて産卵率が上がっていきます。冬を越え、鶏がまた卵を抱く姿を見て、昔の人々は喜びとともに春の訪れを感じたことでしょう。
ちょうど今頃、節分までの寒の内に生み落とされた「寒卵(かんたまご)」は、貴重なもの。寒中に産まれる数少ない卵は、母体の中でゆっくり時間をかけて成熟していくため、栄養価が高く、味も濃厚になります。よって、昔から大寒の時期に生まれた卵は、「大寒卵(だいかんたまご)」と呼び、「食べると健康に暮らせる」と言い伝えられています。大寒卵で卵かけ御飯!これ、最高の贅沢ですね。
ところで、鶏の先祖は野鶏(やけい)とよばれる雉の仲間だそうです。そういえば、第六十九候「雉始雊(きじはじめてなく)」でキジを描き、今回ニワトリを描いていて気づきました。似ている!鳴き声も「ケーンケーン」と「コケコッコー」。ルーツが近い気がします。
さて、日本人が鶏の肉や卵を食するようになったのは江戸時代から。それ以前は殺生を禁じる仏教の影響から牛、馬、犬、猿、鶏などを食べることが禁じられおり、鶏から生まれる卵もこの中に含まれていました。ところが、江戸時代に入り、無精卵は孵化しないということがわかったことで、卵を口にすることは殺生には当たらないと解釈され、その頃から多くの卵料理が誕生し、養鶏も盛んになったということです。ありがたいことです。
かつては夜明けを告げる霊鳥として神聖視され、その鳴き声や姿の美しさを楽しむためだけに飼われていた鶏が、今や私たちのお腹を満たすだけの存在になってしまった。日々の「おいしい!」の幸せは、殺生の上に成り立っていることを忘れてはいけませんね。七十二候を読み解くたびに、人間の身勝手さと自然のありがたみが身に沁みます。
さて、七十二候も最終候。72に区切られた季節の小窓に、今度はどんな景色がめぐってくるのでしょうか。変わらぬものと変わりゆくもの。今という時を重ねながら、そのサイクルが永遠に続くことを願ってやみません。